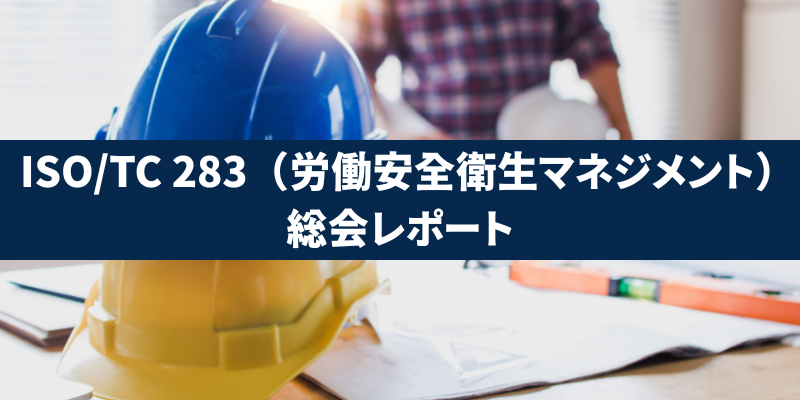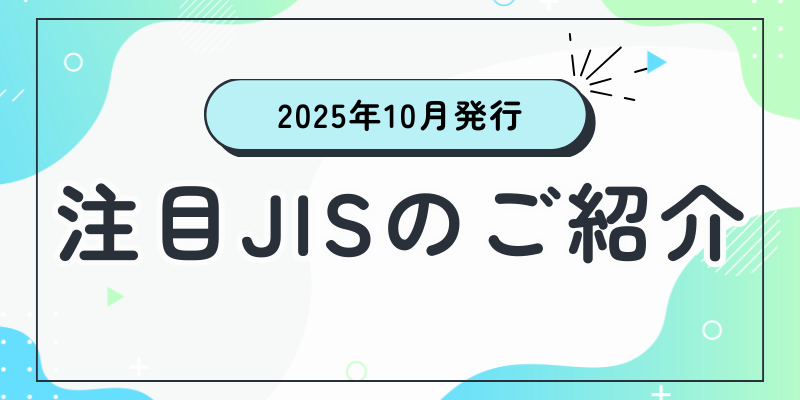
2025年10月発行の注目JISをご紹介いたします(JIS B7610,JIS B7616,JIS C 4442,JIS K6266)
2025/10/24
一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)が2025年10月に発行した注目のJISを、各規格の発行に至った背景とともにご紹介いたします。
JIS B 7610:2025
【改正】
重錘形圧力天びん
Pressure balances
■JIS B 7610はなぜ改正されたのか?
この規格は、単純型構造又は内包型構造のピストン・シリンダを装備し、直接荷重式で、圧力範囲の上限が100 kPa~500 MPaのゲージ圧力及び絶対圧力の計測に対して用いる重錘形圧力天びんの性能を確保するために必要な計量・技術上の要求事項及び試験方法について規定し、1994年に発行されたOIML R110を基に2012年に改正されたものです。その後、2013年にJIS B 7616(重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法)が制定されたことから、有効断面積の決定に関する規定で重複している事項は、JIS B 7616を引用し重複規定を避ける必要があります。また、不確かさの規定についてもJIS B 7616の規定が適用できる事項については、JIS B 7616を引用することとし、重複を避ける必要があります。このほか、同じ圧力計に係り、デジタル圧力計の特性試験方法及JIS び校正方法について規定したJIS B 7547が分割制定されたのに伴い、これへの整合を図る必要があります。
このような状況から、関連するJISとの調整を図るとともに実態に即した内容に改正する必要がありました。
■JIS B 7610の改正に期待されること
この改正によって、圧力計関係規格との整合が図られるとともに、重錘形圧力天びんの信頼性が向上し、継続的に計量性能が担保された製品が市場に供給されることが期待できます。
JIS B 7616:2025
【改正】
重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法
Operation and calibration procedures of pressure balances
■JIS B 7616はなぜ改正されたのか?
この規格は、単純型構造又はそれに準じるピストン・シリンダを装備し、直接荷重式で、圧力範囲の上限が100 kPa~500 MPaのゲージ圧力及び絶対圧力計測に対して用いる重錘形圧力天びんの、性能を確保するための使用方法及び校正方法について規定し、2013年に改正されているが、その後、同じ圧力計に係り、デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法について規定したJIS B 7547が分割制定され、主としてJIS B 7610及びJIS B 7616で定められた重錘形圧力天びんを標準器としてデジタル圧力計を校正する方法が定められています。しかし、圧力計測に関わる用語の使い方などに一部不整合があるため、この規格においてもこれらの圧力計測に関連するJISに整合する必要があります。また、同時に改正を行うJIS B 7610(重錘形圧力天びんの製造と精度等級のJIS)で規定している有効断面積の決定に関する規定や不確かさの規定において、相互の規定内容に重複がないような規定とすべきとの指摘があり、規定の振り分けを行う必要があります。さらに、与えられた発生圧力値を補正して計算する場合の式を改める必要があります。
このような状況から、近年の技術の実態に即し、より適正な校正が可能となるJISに改正する必要がありました。
■JIS B 7616の改正に期待されること
この改正によって、圧力計関係規格との整合が図られるとともに、重錘形圧力天びんの校正及び不確かさ評価方法の統一、高度化が進み圧力の計量トレーサビリティの確保と各種圧力計の製品評価精度の向上に資することが期待できます。
JIS C 4442:2025
【制定】
電気エネルギー貯蔵システム-電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項-電気化学的システムの計画外変更の実施
Electrical energy storage (EES) systems-Safety requirements for grid-integrated EES systems-Performing unplanned modification of electrochemical based system
■JIS C 4442 制定の背景
電気エネルギー貯蔵システムにおいて、特に近年は大型蓄電池による蓄電システムが市場の拡大を見せ、既に導入から数年以上を経過している設置済み蓄電システムの数が増えています。蓄電システムの寿命は10年単位と長期間が想定され、その期間中に当初想定から外れる変更・改造を加えたいという需要が発生しており、このような改造・変更を実施したとしても安全を担保する方策が切望されてきました。また同時に、電気自動車等での一次利用を経た電池(二次利用電池、再利用電池、転用電池などと呼ばれる。)を、蓄電システム内部において改めて使用する需要が拡大しているが、このような電池は内部の状態が個体ごとに大きく異なることから、これらを蓄電システムにて安全に使用する場合は、新品電池を使用する場合とは異なる対応が必要です。
これらの背景を鑑み、国際規格開発を先行して進めることとして日本から国際提案したIEC 62933-5-3が既に令和5年10月に発行されていることから、今般、蓄電システムの安全向上を図り、蓄電システムの導入を進める関係者からの要望も踏まえ、国内での対応を国際的なものとして普及を図るためにもJISを制定する必要がありました。
■JIS C 4442の制定に期待されること
当該規格を制定することにより、我が国の安全性の高い蓄電システム製品の製造や輸出が促進され、国際競争力の強化に寄与するとともに、より安全な蓄電システム製品の開発・製造が可能になることから、蓄電システムの利用者の安全及び施工業者の労働安全の向上に寄与することが期待できます。また、IEC規格との整合化を図ることにより、国際貿易の円滑化に寄与することが期待できます。
JIS K 6266:2025
【改正】
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-耐候性の求め方
Rubber, vulcanized or thermoplastic-Determination of resistance to weathering
■JIS K 6266はなぜ改正されたのか?
この規格は、加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの、屋外暴露試験及び実験室光源暴露試験について規定し、さらに、暴露後の試験片の色、外観、物理特性などの変化(耐候性)を求める方法について規定したもので、2007年にISO 4665:2006を基礎として改正されました。その後、ISO 4665は2016年に改訂され機械的性質の評価方法として技術の進展により新たに圧縮永久ひずみが追加されました。また、ISO 4665にはJIS K 7219の対応国際規格ISO 877が暴露方法として引用されているが、ISO 877:1994は2009年に三つに分割制定されました。ISO 877の分割制定に合わせてJIS K 7219の分割の際、ISO 877-3の太陽追跡集光暴露試験は国内の気象条件に合わず使用されていないためJIS K 7219-3の制定は見送られ、JIS K 7219-1及びJIS K 7219-2だけが制定されたことも踏まえ、太陽追跡集光暴露試験を削除する必要があります。
このような状況から、対応国際規格との整合を図り、近年の技術の実態に即した規定内容とするため、JISを改正する必要がありました。
■JIS K 6266の改正に期待されること
・対応国際規格との整合を図ることによって、最新の技術水準が反映され、品質改善に寄与することが期待できます。
・市場の実態に合わせた改正を行うことによって、市場の混乱を防げるだけでなく、取引の単純公正化にも寄与することが期待され、規格利用者の利便性の向上が期待できます。
・製品の評価が最新の技術水準によってなされることによって、製品の信頼性の向上も期待され、国際競争力強化にも寄与することが期待できます。
[日本規格協会]