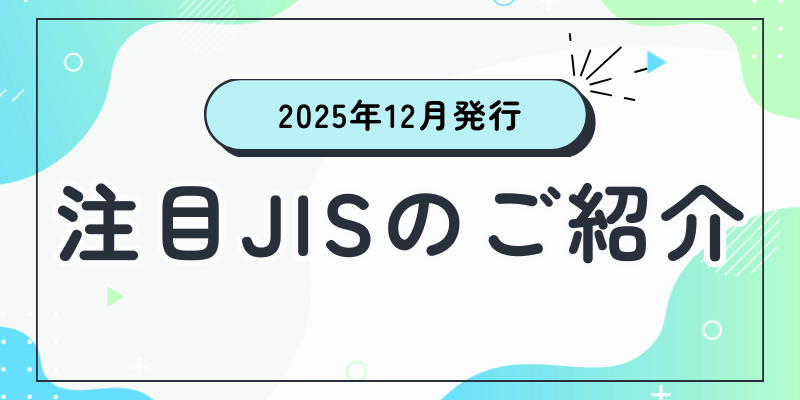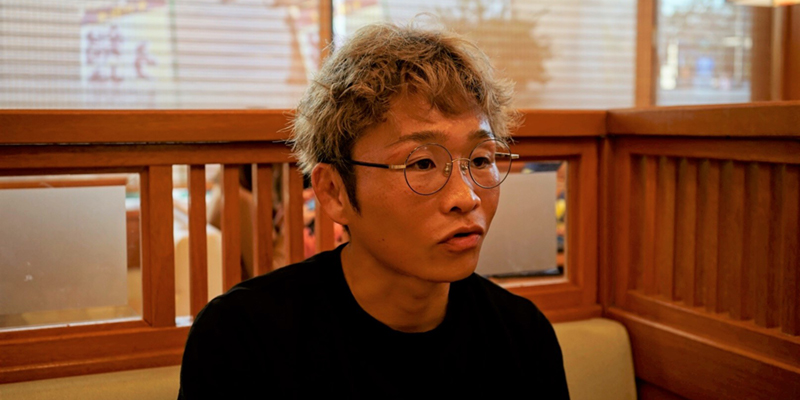
キックボクシングチャンピオン駿太に学ぶプロセス改善(後編)
2020/01/28
前編では駿太選手にプロアスリートとしてのPDCAの回し方や顧客満足を念頭に置いた目標設定、原因分析やカイゼンなどについてお話を伺いました。
後編では情報発信による効果を中心にお伝えします。

プロアスリートと情報
J:駿太選手のYouTubeを拝見すると、様々な試行錯誤をしているのがわかります。
駿:ありがとうございます。YouTubeは選手としてのレベルアップに非常に役立っていると思います。動画のためにデータを取ることなんかは特にそうですね。
J:何のデータですか?
駿:選手活動に関することなら、あらゆるデータを取っています。例えば、取った食事のカロリーや栄養素、その結果の身体の変化なんかです。自分のやっていることが感覚になってしまうのが怖いんですよ。このくらいは食べても良さそうだとか感覚的に考えてしまうのは危険なので、数字で把握することは重要だと思います。
J:感覚に頼るのではなく、客観的なデータ分析が重要ということですね。これも、ビジネスに通ずる ものがあります。
駿:そうですね。
J:こうしてインタビューしていても、駿太選手は話し上手で、YouTubeのチャンネル登録者が多いことも納得です。
駿:とんでもないです。そもそも自分の口下手を何とかしたくて、一種のトレーニングとして始めたものなんですよ。ただ、あれこれ考えるだけでなく、言語化して発信するというのはとても意味があると感じています。自分自身の頭を整理できますし、様々な気づきを得られますね。
J:口下手だったなんて、とても信じられないです。
駿:もともと目立ちたがり屋ではあるんです。以前、成功している人はみんな本を読んでいると思って、自分も1カ月に15冊のペースで読書するようになりました。そこから得たインプットを発せないことがストレスになってきて、YouTubeを始めました。今はチャンネル登録者が増えることが大きなモチベーションになっていますし、ファンの人たちがどういうことを求めているかを知るためのマーケティングツールにもなっていますね。あと、情報の特性というか、記憶の特性なのですが、人は忘れるじゃないですか。なので、同じ情報を繰り返し伝えている部分はあります。ただ、同じ情報でも時間を置いて他の切り口で取り上げることで、新しいものに見えたり、自分でも忘れていた部分を定着させることができたり、伝え方をブラッシュアップすることにもつながっています。
J:良いこと尽くしというわけですね。情報の言語化にもカイゼンの思考が伺えますね。
駿:はい。自分の動画を自分で見たり、人に見てもらうことで、自分が客観的にどう見られているかわかるというのも大きいです。最近、食事している動画を上げたところ、「いただきますを言った方がいい」というコメントをもらって、ハッとなりました。自分の行動の反省とか振り返りのツールにもなっていますね。それに、辛らつなコメントを読むことで、メンタルトレーニングもできている気がしますし、自分の成長プロセスを人に見てもらうことで、他人にもプラスの影響が与えられれば、と思っています。
J:YouTubeはいわゆる「メタ認知」の訓練にも役立っているんですね。自己コントロールの手法は試合にも役立ちそうです。駿太選手が動画を毎日アップされているその継続性、習慣化が他の選手には真似できないところだと思います。
駿:そうですね。習慣化の仕方や悪習慣を断つ方法などはよく質問をもらいます。自分自身、悪習慣から立ち直った経験があるので、必ず変えられると思っています。あと、YouTubeは閲覧数など様々なデータが取れるので、検証に打ってつけなんです。PDCAのサイクルはここでも活かしています。
5日検証生活も自身のトレーニング等におけるPDCAの一環として行っている。
J:今後もYouTubeは続けていくつもりですか?
駿:もちろんです。選手を引退した後もYouTubeで何かビジネスをしていきたいと考えているんですよ。キックボクシングを教えることは嫌いではないですが、そこまで興味はありません。自分にとって最も重要なのは、新しいチャレンジをして成長すること。その時間をいかに長く積み重ねていけるかが人生の幸せだと考えています。
J:どうもありがとうございました。これからも頑張って下さい。

キックボクサー
谷山ジム所属。第15代マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟フェザー級王者、第2代WMAF世界フェザー級王者。プロキックボクサーとして活動する傍ら、Youtuberとしても活動し、自身のトレーニング経験を基にした栄養や健康に関する情報を発信している。