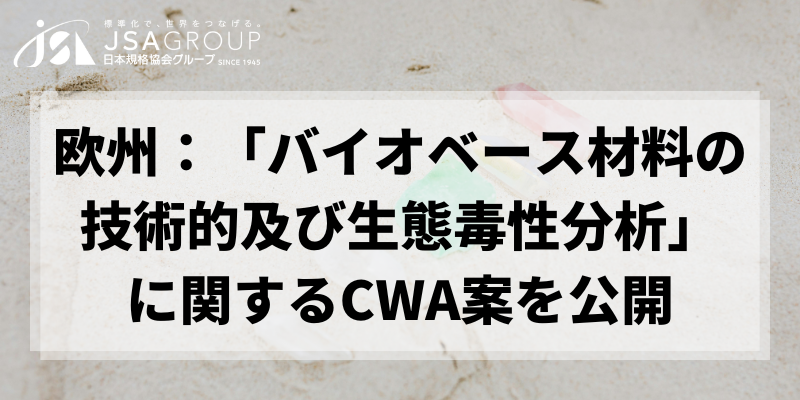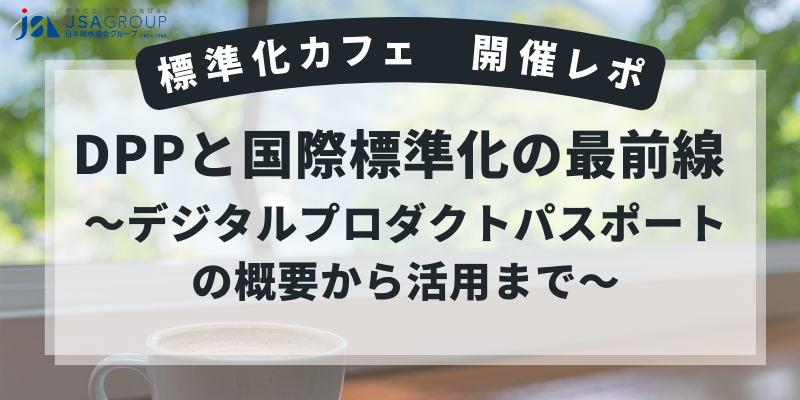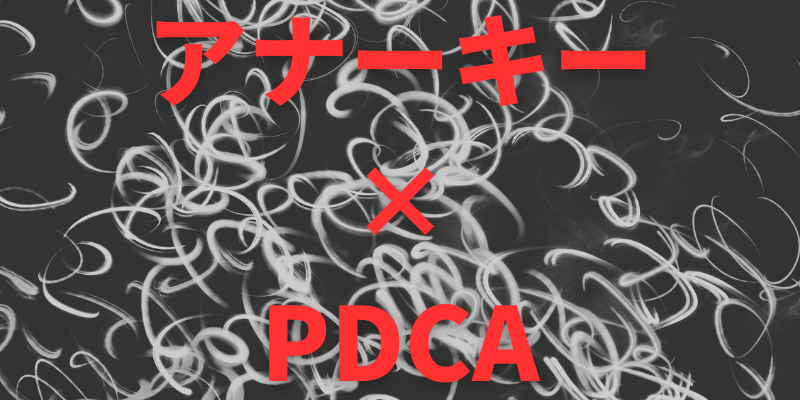
アナーキーなPDCAのために 哲学者 千葉雅也
2023/06/05
★アンコール掲載(初掲:2020/02/03)★
『標準化と品質管理』という媒体から原稿依頼を受けたのだが、僕は物事を一定のフォーマットに収めなければならないという要請が大変キライで——スーツを着るなんてまっぴらごめんなのだ——、仕事においてもその都度のニーズによってインフォーマル(非定型的)に対応することこそが重要だと思っているから、「標準化」とか「規格」といった観念に対して懐疑的なことを書いてもいいかと尋ねた。すると、それでもいいとおっしゃるのでお引き受けした。
僕は立命館大学の先端総合学術研究科という大学院に勤めており、現在は副研究科長を担当している。研究科長と副研究科長の二人が執行部と呼ばれ、研究科全体の管理運営にあたっている。
今日の大学は標準化・定型化の「波に襲われている」と僕はネガティブに表現したい。たとえば、誰が担当しても同等の教育効果が得られるように授業内容を固定したがるようなのには反発を覚えるし、また運営においても、節目節目で統一フォーマットのPDCAの書類を書かされることにはうんざりしている。なぜか。理由は単純だ。個々のメンバーから自律性とプライドが奪われ、個人が交換可能なコマと化していくからだ。
ところで、僕個人として執筆の仕事をどうしているのかだが、実は僕も個人的にはPDCAサイクルを日々回し、事細かに記録を書き残している。つねに中長期的なプランを立てて動いているし、ひとつの原稿を仕上げるまでの工程をアウトライン・プロセッサに記録しておいて後で同様のやり方を再現可能にしようとしている。
大規模組織の形骸化したPDCAにはうんざりなのだが、個人的にはPDCA的な発想はある意味当然のこととして実践しているわけである。そこで今回は、PDCAに関する組織と個人の間のギャップについて少し書いてみたい。
個人としての仕事でも、品質の向上と維持のためには、計画し、経過をモニタリングし、振り返ることが必要なのだが、大事なのはそのやり方をガチガチに固めてしまわないことだ。PDCAを可塑的なものとして回すこと。そのことに気づくのがキャリアにおける重要な進歩だと僕は思う。ビギナーはしばしば、どこかで見聞きした実績のあるらしいメソッドに飛びつき、その通りにやろうとするものだ。最初は「その通りにやること自体の楽しさ」でテンションが上がるのだが、逸脱的な事態がすぐに発生して、やり方を維持することがかえって不効率になる。
方法を固定し、その枠内で「内容」を作るという考え方ではダメだ。方法(形式)と内容は、連動して変化していくのが自然なのである。
何においても、人は同じやり方を続けることで安心する。それは儀礼である。儀礼的なものなしでは、おそらく人は生きられない。けれどもある段階で、儀礼をなくすのではないにしても、儀礼は変更可能だと気づくべきなのだ。
PDCAプロセスの回し方自体がプロジェクトの進行中に再検討され、記録の仕方もリアルタイムで変わっていくのが自然である。キーワード的に言えば「PDCAサイクルの可塑性」が大事で、また「PDCAに対するメタPDCA」が必要なのである。が、それを大規模組織でやるのは難しい。方法を変えるにはいちいちメンバーの承諾を得なければならないからだ。
大規模組織ではどうしても統一的なフォーマットが必要になり、必然、それは形骸化する。計画書を書け、報告書を書け、というだけの話になる。そして「それっぽく」書けばいいというだけの「ごっこ」になる。まさに儀礼である。
実質的なPDCAは個々人が回しているのだ。
個々人のたえず変化するPDCAをどうやって、どのくらいの規模で共有したらいいのだろうか。ともかくトップダウンで書類提出を強いるのではダメだ。ボトムアップでなければならない。少人数のチームなら、普段のちょっとした会話でそれぞれの状況把握を共有することができる。僕も同僚とおしゃべりをするときにこそ、上から振り返りを求められるときなどよりずっと実質的で濃い思考をしている。その思考をどれだけ上位の意思決定に接続できるか。他方、トップダウンの長期的なプロジェクトも当然あるから、ボトムアップとトップダウンがうまくミートするところを探らなければならない。
とはいえ、組織全体が意思統一されることなどなく、各所に異なる思惑があり、それに応じて各所が「秘密」を持っているのが現実である。大きくトップ/ボトムに分けても、トップ側の利益とボトム側の利益はしばしば対立し、それぞれに秘密があるから、組織全体で共有可能な書類は、双方の秘密をごまかすための「取り澄ました文体」になる。いわゆる官僚的な文体は、複数の秘密の間に成立する緩衝地帯である。
形骸化したPDCAの書類作成、すなわち「PDCA儀礼」とは、そもそも内部に複数の対立を孕む組織を、全体として意思統一して管理できている「かのような」幻想を維持することである。
極論を言えば、まったく無計画な人間などいないのであり、一見ちゃらんぽらんに生きているような人間であれ、その人生には潜在的なPDCAサイクルがある。上からフォーマットを押しつける前に、「見えないPDCA」を掘り起こす必要があり、その多様性を組織でどう活かすかを考えなければならない。だから「PDCAのダイバーシティ」も重要なのだ。多様で可塑的なPDCAをボトムアップで……と考えると、アナーキーとも言える組織の可能性が浮かび上がってくる。それは少人数ならば可能なのだが、繰り返しになるが規模が大きくなると難しい——そしてさらには、社会、国家、世界という規模にまで広げて考えてみたらどうだろうか。
多様で可塑的なPDCAをボトムアップで。どうしたらいいのか。それは、するどく政治哲学的な意味でのアナーキズムの問いに他ならない。

哲学者、作家、立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授
主な著作に『動きすぎてはいけない——ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(紀伊國屋じんぶん大賞、表象文化論学会賞)、『勉強の哲学』、『意味がない無意味』、『アメリカ紀行』、 『デッドライン』(野間文芸新人賞)がある。