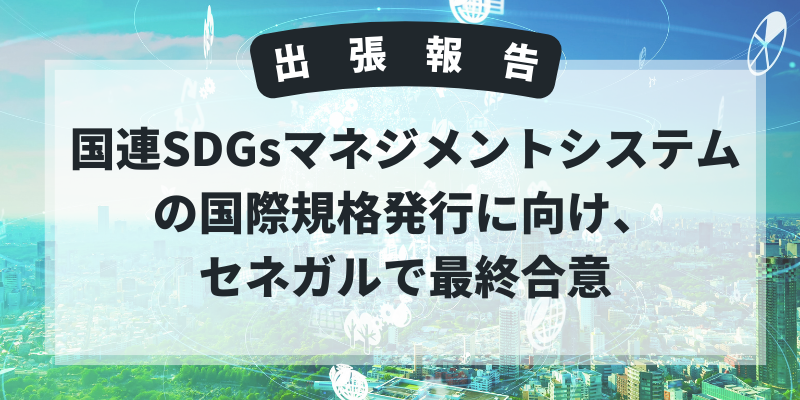ギネス世界記録™における標準化について
2023/07/27
★アンコール掲載(初掲:2019/05/13)★
今回、ギネス世界記録における標準化というお題を頂きました。われわれにとっての「標準化」の意味することは、他の方から見ると、かなりユニークかもしれません。そこで「ギネス世界記録における標準化」についてご説明する前に、そもそも、まずギネス世界記録とはどんな組織か、ということについて説明をさせてください。
ギネス世界記録は、世界一の審査、認定を行っている組織です。始まりは、1951年、アイルランドで狩猟を楽しんでいた当時ギネス醸造所の最高経営責任者だったヒュー・ビーバー卿の頭に浮かんだ疑問―――「 ヨーロッパで最も速く飛ぶ狩猟鳥はどれか? 」でした。この答えを自分の蔵書では探せなかったビーバー卿は世界一を集めた本を作ったら面白いのではないか、と考え、1955年、”The Guinness Book of records” 現在の『ギネス世界記録』が誕生いたしました。
自然、動物、科学、スポーツなどありとあらゆるジャンルの世界一を集めた本書籍は、発表されるやいなや評判となり、その後毎年発売され、瞬く間に全世界へ広がり、現在にいたります。書籍は現在、約40の言語に翻訳され、100か国以上の書店に置かれています。また、書籍発行からの60数年の年月でデータは蓄積されており、登録されている世界記録は5万件を超えています。また、現在の組織はギネスワールドレコーズ社として独立して活動しており、今やこれら世界一の情報は書籍のみならず、TV、イベント、デジタルプラットフォームなどより多くの形で全世界の皆様に届けられています。
皆さまも、もしかして今までギネス世界記録認定!といったニュースや情報に触れたことがあるかもしれません。そして、本当に様々な記録があることに驚いたかもしれません。多種多様な記録を測定し、登録しているのはなぜか。それは、「だれもが世界一になる可能性を秘めている」という我々の考え方に基づいています。ギネス世界記録は、主観や一般的な通念で人々の試みや挑戦を除外しません。その結果、我々の元に世界中から送られてくる「世界一」の情報や申請は本当に様々あります。ではどのようにその中から世界一を定義化し、登録していくのか。
いよいよ本題に入りますが、われわれが大切にしている基軸が4つあります。1つは測定可能なこと。計測できないものはギネス世界記録の対象となりません。2つ目は証明可能なこと。ギネス世界記録では証拠物を重んじており、証明ができないものは記録となりません。3つ目、標準化可能なこと。こちらに関しては後から詳しく説明させてください。4つ目は更新可能なこと。記録は常に進化、更新していくことが求められます。
さて、3番目にありました「標準化可能」という点。これはつまり、世界中の誰もが同じ条件のもとで挑戦可能な土俵になっているか、ということです。自分が作ったこのアイテムで、この場所でしか出来ないこんな挑戦で世界一を目指します、という申請がきたとしても、それは却下となるわけです。
記録挑戦の標準化をするにおいて重要な役割を担っているのが、記録ごとに作成される「ガイドライン」となります。ガイドラインには、記録内容の定義、及び、挑戦をする際に使用する物品や挑戦方法の規定が記されています。
例えば、ある時間以内に行なったハイタッチ(high five)の回数、という記録案の場合、まずハイタッチという行為を標準化することができるか、という点が検討されます。ハイタッチは、2人の人間が同時にお互いの手のひらを叩き合う動作、として定義づけできますが、ハイタッチ、という名前が示すように、高い位置での動作である必要があります。そこで、手を上げる高さの標準化をするために、二人の間で背が小さい人の頭の上で行なうこと、そして、手を合わせるだけでなくパチンと音が出ること、などの規定もガイドラインに加えられます。記録挑戦の審査をする際には、これらのガイドラインの規定に則り審査され、有効とみなされたハイタッチのみ記録数とカウントされることになります。
その他、よく登場する規定として、「市販されているもの(commercially available)を使用すること」という点もあります。例えば、多数のものをモザイクのように組み合わせて最終的に大きな一つのイメージを作るモザイクアートの記録。記録は使用する物の種類によって分かれていますが(シャツモザイク、コースターモザイク、クッキーモザイク、など)、記録挑戦者自身が、記録のためにデザインや色づけしたものを使うのではなく、市販品に手を加えない状態で使用することがルールとされています。「市販品」をくくりとすることで、挑戦のために独自に作り出されたアイテムの使用を防ぎ、記録挑戦のルールを標準化していると言えます。
また、記録内容によっては、「市販品」が第一の規定にあり、そこから、サイズや重さ、など、さらに細かい規定が加えられるケースもあります。その場合、国によって基準とされているサイズが異なることも多々あるため、世界で平均的に使われているサイズを調査し、その範囲内のものの使用をルールとしています(例:90 mm x 90 mm から 100 mm x 100 mm以内のものであること、など)。
ギネス世界記録のガイドラインは厳しいと言われることも多いのですが、「標準化」を大切にしているのは、全世界から挑戦を受け付けるギネス世界記録ならでは。標準化無しでは記録の根本が崩れてしまいます。世界一と確認し、登録するために、このような定義化をギネス世界記録では行っています。

ギネスワールドレコーズジャパン記録管理部 ディレクター/公式認定員
2007年、英国本社ギネスワールドレコーズに入社。日本人初の公式認定員となり、記録認定のために、英国をはじめとしたヨーロッパ各国、日本、アメリカ、インド、台湾、アラブ首長国連邦等、世界中を飛び回り、今まで約500の記録挑戦に立ち合う。2012年、日本支社に異動。2014年5月から現職。好きな記録は「ハイヒールで走る100m最速記録」(13秒557)。上智大学外国語学部英語学科卒。プライベートでは、ネコと音楽をこよなく愛するベーシスト。

![[日本提案のISO/IEC規格]ISO 24359-1(建物のコミッショニングプロセス計画第1部:新築建物)ほか 2026年1月](/img/membercontents/1648_top.png)