
災害食の国際標準化の最新動向
2024/02/28
はじめに
2024年元旦の日本を襲った能登半島地震。震度7を観測し,3万人超の避難者が発生した。そして再び,被災地では食料の不足が繰り返されてしまった。避難者の生命をつなぐため,健康で生活するためには食は必須である。しかし,食が後回しになる事態が頻発している。食を後回しにしない対策の一つとして,まさに今,災害食の国際標準化を進めている真最中である。
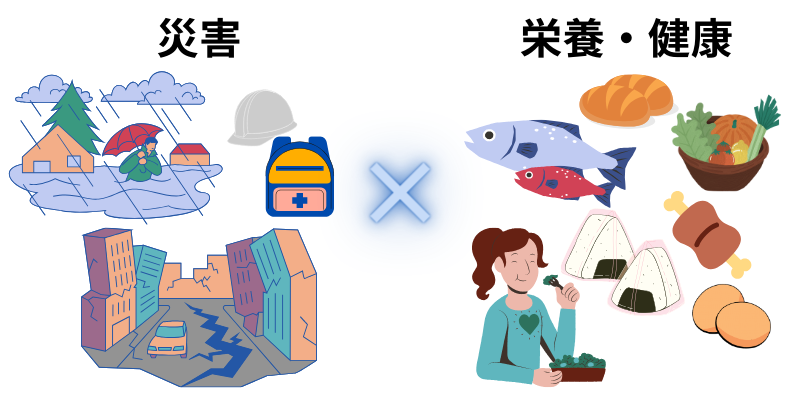
ISOでの議論がスタート
2021年に日本国内に災害食国際規格委員会が 設置され,日本主導による国際標準化の検討を行ってきた。この結果,2023年7月にISOの専門委員会であるISO/TC 34(食品)において,「災害食の品質要求事項」を新たな作業項目として提案するに至った。
各国からの投票の結果,賛成多数により,2023年10月にこの作業項目が承認された。現在,ISO/TC 34内の作業グループ,WG 25(緊急・危機的状況における食料安 全保障)で規格開発の議論がスタートしたところである。新たな作業項目の承認にどれだけ意義があるのかと思われるかもしれないが,新たな国際規格を策定するに当たっては,各国の賛同とその作業に積極参加する意思を得ることが最初のプロセスで求められており,3か月にわたる国際投票を通じ,ISOの加盟国によって,この提案に賛成するか,国際標準化の作業に参加するのかの票が投じられた。今回は,賛同と積極参加という各国からの一定の理解が得られたという点で,一定品質の災害食を世界で広めるための大きな一歩と言える。蓋を開けてみたところ,当初想像していた以上の国々からエキスパートが参加してくださり,各国の熱気とともに熱い議論が始まったのである。
「災害食の品質基準」の国際規格化は,日本の経験や教訓をもとに日本がリードしてきた災害食の世界標準作成の実現につながり,災害食の国際マーケット拡大が期待される。また,災害にともなう栄養不良,栄養格差,健康被害を減らすための一助となること,災害対策の仕組みとして備蓄習慣を海外に普及することが可能となり,日本が持つ災害食の知見を世界に発信する機会が多くなることも期待される。
日本が,①取組みでリードして,②技術開発でリードして,③ルールメーキングを行い,④産業で勝つ!未来に向けて進めていきたい。
この記事は, 『標準化と品質管理(SQ誌)』2024年春号で続きをご覧いただけます。
[ジュネーブ事務所]

TSUBOYAMA(KASAOKA)NOBUYO
管理栄養士,医学博士
《現所属》
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所 国際栄養情報センター
国際災害 栄養研究室 室長
《経歴》
1991年 東京家政大学 管理栄養士専攻 卒業。1997年 高知医科大学大学院 博士課程 修了。1999年~ 国立健康・栄養研究所 入所。2018年4月~ 現職 (日本の政府関連機関で初めての災害栄養を専門とする部署を立ち上げる)。分子栄養学研究を経て,災害時の食・栄養問題について研究。



