
「スマートな悪」に抵抗する規格の可能性
2023/06/22
古代ギリシャの哲学者プロタゴラスは、「人間は万物の尺度である」と語った。私たちが認識するものは、すべて、人間の認識能力によって条件づけられている。その条件に適さないものを認識することはできない。たとえば、人間には素粒子を見ることはできないし、20Hz以下の周波数を聴くこともできない。しかし、同時に人間はそうした条件を他者と共有してもいる。「私」に見えているものは他者も見ることができる。自分に見えているものが、自分にだけ見えているわけではない──そう信頼できることが、世界にリアリティを与えるのだ。
プロタゴラスのいう「尺度」は、「規格」という概念にも通底するものだろう。人間は、人間的な認識能力という共通の規格を備えた存在である。そうであることを前提にして私たちの社会は設計されている(だからこそ、そうした規格を持たない者は、社会から排除される)。ここには、規格という概念に備わる二つの側面が示唆されている。
第一に、それが私たちの経験を閉ざす、ということである。人間の認識能力は、私たちの世界の経験を制約し、その規格のもとに拘束する。私たちは、人間である限り、この条件の外側に出ることができない。しかし、第二に、それは同時に私たちの経験を開いたものにもする。なぜなら、そうした規格に基づくからこそ、他者と経験を共有することができるからだ。
何かに規格を与えることがもつ、閉鎖的な力と開放的な力──それは、決して背反するわけではない。しかし、一方が他方を圧倒することもあるだろう。たとえば、その閉鎖性が全面化されるとき、そこにはスマートなシステムを組織する力が作動し始める。そして私たちは、そうしたスマートさを美徳とする社会に生きている。
たとえば日本政府は、日本の科学技術イノベーションが向かうべき未来像として、Society 5.0という概念を提唱している。これは、現在の情報社会の後継に位置する社会であり、ICTを活用してデジタル空間とフィジカル空間の融合を実現した、「超スマート社会」に他ならない。この未来像においてスマートさは、規範的な概念として、つまりそうあるべき姿を示す概念として、用いられている。
しかしこうした発想は、それに対する慎重な反省を伴わない限り、危険である。なぜなら、スマートさがかえって不正義を強化し、再生産し、効率化することもありえるからだ。
たとえば、第二次世界大戦中のドイツにおいて、ナチスの将校であったアドルフ・アイヒマンは、ユダヤ人の強制収容所への輸送を指揮していた。彼は、国内にいた大量のユダヤ人を効率的に輸送するために、緻密な計画を立て、ロジスティクスを設計し、最適化されたシステムを作り上げてみせた。彼は紛れもなくスマートだった。しかし、それは組織的な大量虐殺を引き起こしたのである。
戦後、アイヒマンは罪に問われ、裁判にかけられた。法廷で彼は次のように証言し、無実を訴えた。すなわち、自分はあくまでもナチスという巨大な組織の歯車に過ぎなかった、ただ与えられた仕事に最適解を出しただけだった、だから自分には責任がない、と。スマートなシステムを作り出した彼自身が、自分自身さえもそうしたシステムの一部であると見做していた、ということである。
スマートなシステムとは何だろうか。おそらくそれは、余計なことを考えず、細々した調整を必要とせず、半ば自動的に目的が達成されるようなシステムだろう。ヒューマンエラーは起こらないし、トラブルの対応も必要ない。人間から思考すること自体を免除してくれるもの──それがスマートさなのだ。だからこそ、スマートなシステムの歯車だったアイヒマンは、思考しなかった。自分が行なっていることの道徳的な意味を、あるいは自分が手にかけている人々が辿ることになる未来を、想像することさえしなかったのである。
政治思想家のハンナ・アーレントは、このように思考が欠落した結果、組織的な犯罪に加担してしまう事態を、「凡庸な悪」と呼んだ。しかし筆者は、その思考欠如はアイヒマンの凡庸さによってもたらされたのではなく、彼のスマートさが引き起こしたものだと考える。アイヒマンのうちに見出される悪は、いわば「スマートな悪」なのだ。
規格化のもつ閉鎖性は、こうしたスマートな悪へと連続するものである。物事をある特定の規格のもとでしか捉えられなくなるとき、私たちの判断はその規格のもとに閉ざされ、最適化される。そのとき、別の規格がありえるのではないか、という想像力を維持することは困難になる。そうした配慮を一切不要とすることこそが、スマートさだからだ。
しかし、前述の通り、規格化にはもう一つの側面もある。それは、他者との関係性を作り出すという側面、すなわち開放性である。アイヒマンは自らを歯車に喩えた。しかし、規格が設けられているということは、そこに別の部品を当てがい、システムに違った機能をもたらすこともできる、ということである。規格が共有されているからこそ、システムに対して、その外部にあるものを接続することが可能になるのだ。
どうしたらスマートな悪に抵抗できるのだろうか。システムと呼ばれるものをすべて放棄するのが、一つの道だろう。しかしそんなことは現実的には不可能だ。そうであるとしたら、システムのなかに留まりながら、そのシステムの外部にあるものと、他者と、つながりを保ち続けるための手段を確保する以外に、方法はないだろう。そしてそのためには規格が必要なのだ。そうした、開かれた規格化を目指すことが、倫理的に望ましい姿ではないだろうか。

1988年、東京都生まれ。関西外国語大学准教授。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。主著に『スマートな悪:技術と暴力について』(講談社)。
SQオンライン のおすすめ記事
-

ISOは10月7日、ISO 17298「組織のための生物多様性 – ガイドライン及び要求事項」を発表
ISOが生物多様性に関する組織の行動を支援するための国際規格を発行
2025/10/10
-
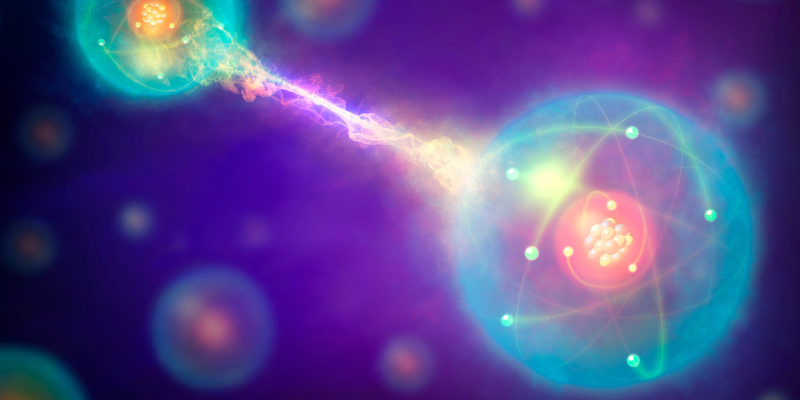
PM2.5及び超微粒子への曝露調査ガイドラインに関するCENワークショップの発足を発表
欧州:「屋内空気中のPM2.5及び超微粒子への曝露調査ガイドライン」に関するCENワークショップの発足
2025/10/09
-

ISO 9001/14001の改訂スケジュール、改訂ポイント、JSAグループの総合支援策を網羅
ISO 9001/ISO 14001 最新改訂情報を掲載した特設サイトがリニューアルオープン!
2025/10/02
